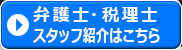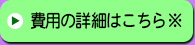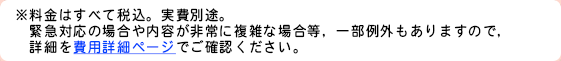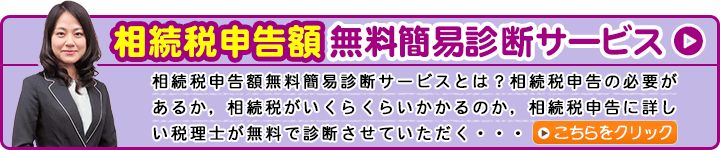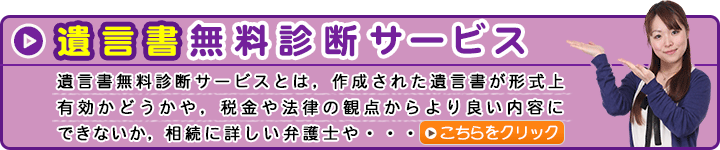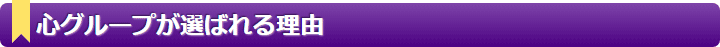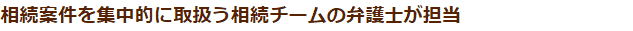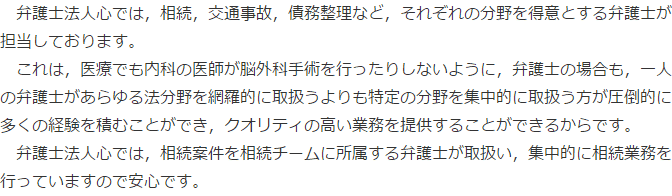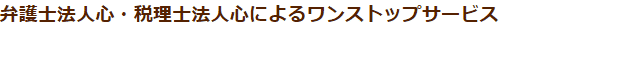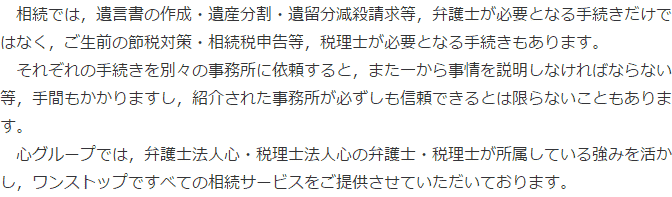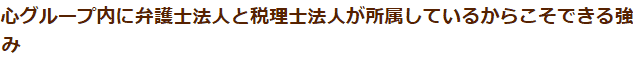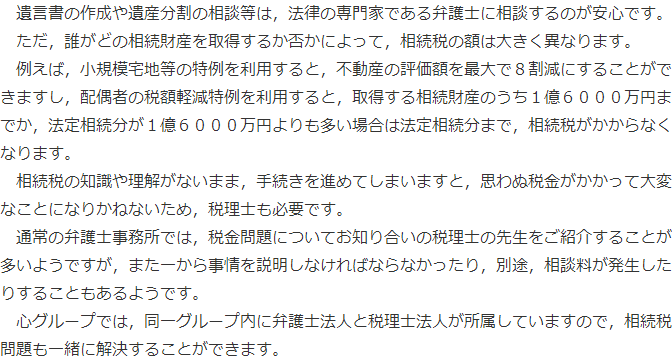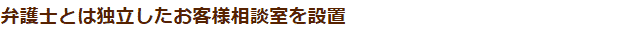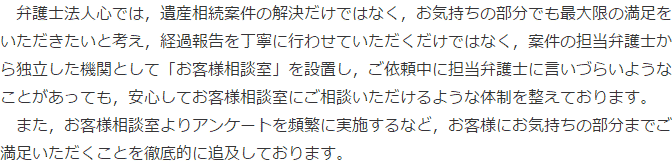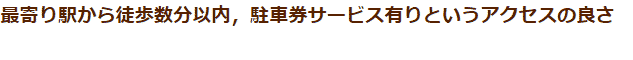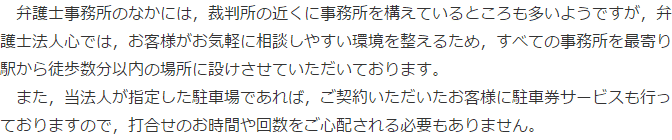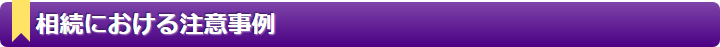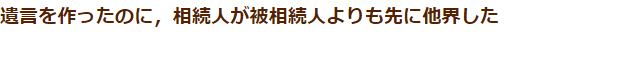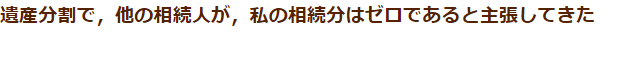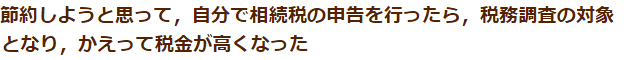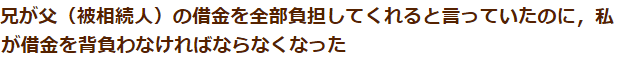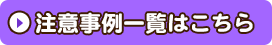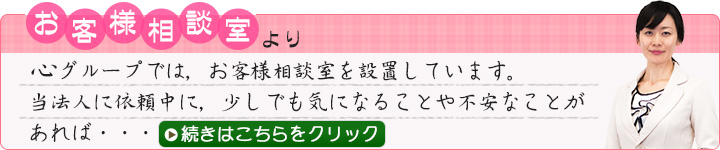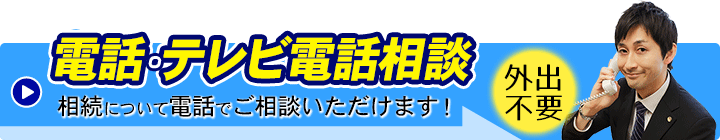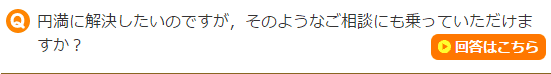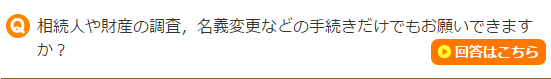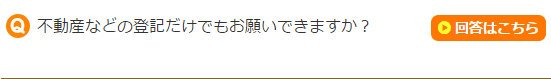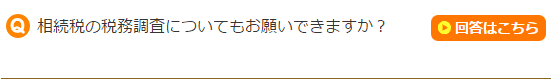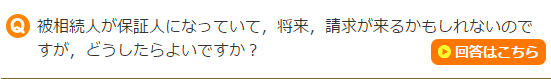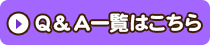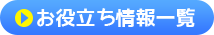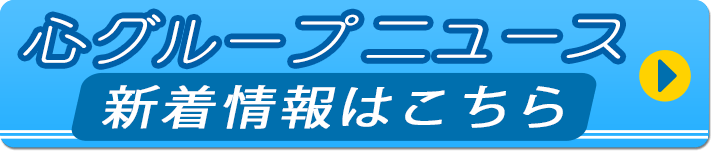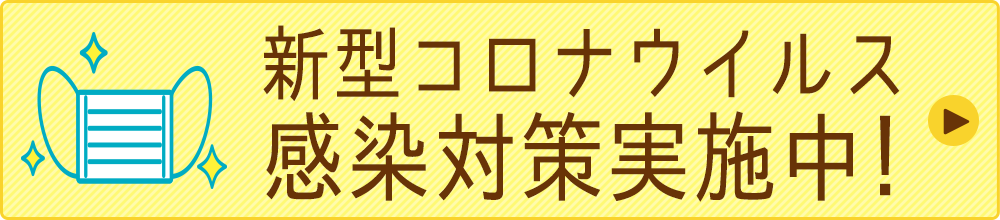名古屋で相続にお困りの方へ
問題を適切に解決するには様々な専門知識が必要となります。私たちは様々なお悩みをトータルサポートできる体制を整えていますので、安心してご相談ください。
注意していただきたい事例
決して特殊なものではなく、どなたにでも起こり得る事例です。どのようにすれば防げたのかも記載していますので、名古屋で相続を控えている方はお読みください。
サイト内更新情報(Pick up)
2024年4月2日
相続放棄
債務の相続のルール
一般的に、相続については、遺言書があれば、誰がどの遺産を取得するかが定まります。一方、遺言が無ければ、相続人全員で遺産分割協議を行うことによって、誰がどの遺産を取得する・・・
続きはこちら
2024年3月5日
手続き
相続預金の払戻し
金融機関は、被相続人が死亡したことを知ると、被相続人名義の預金口座を凍結し、お金を引き出せないようにします。それは、被相続人が死亡するまでの預金は被相続人が自由・・・
続きはこちら
2024年2月2日
遺言
遺言が必要な場合
遺言は、遺言者が自らの意思で作成すれば、基本的には、相続における自らの希望をそのまま実現することができるため、相続においては非常に重要な手段です。そのため、遺言・・・
続きはこちら
2024年1月5日
専門家等
相続対策と専門家
相続対策は、大きく三つに分けることができます。「争族」対策、節税対策、納税資金対策です。「争族」対策は、被相続人となる方が、遺留分等に注意しながら、円満な遺産の分け・・・
続きはこちら
2023年12月4日
手続き
相続手続きで注意すべき期限
人が亡くなると、お葬式や四十九日で忙しくなりますが、法的な期限のある相続の手続きもあるため、注意が必要です。この期限を知らないと、多くの借金を相続することになったり・・・
続きはこちら
2023年11月2日
遺留分
遺留分の期限
相続の発生後は、お通夜、お葬式、49日、1周忌といったように、個人を悼むための行事がたくさんあります。そのため、遺産に関することは、とりあえず1周忌が終わってからと・・・
続きはこちら
2023年10月3日
遺産分割
遺産分割に関するトラブル解決方法
遺産分割の方法には、「協議」「調停」「審判」の3つがあります。協議とは、共同相続人が話合いを行って遺産を分割する方法です。調停とは、協議ではまとまらなかった場合に、調停・・・
続きはこちら
相続の参考情報
参考情報を随時更新しております。相続について、もっと知りたいという方はぜひご覧ください。
仕事帰りにお立ち寄りください
心グループの各オフィスは名古屋駅から非常に近いところがあり、ご相談にいらしていただく際にもとても便利です。「相続に関して相談したいけれど時間がない」という方もご相談いただけます。
名古屋駅からの名古屋オフィス・本部オフィスへのアクセスについて
1 太閤通南口から駅を出ます
【JR線・あおなみ線をお使いの方】
⑴ 太閤通南口前の改札へ向かいます
太閤通南口前の改札が、当オフィスに一番近い改札です。
そのため、電車を降りたら、太閤通南口と書かれた案内に従って改札口へ向かってください。
⑵ 改札を出たら太閤通南口から駅を出ます
改札の正面に太閤通南口があります。
改札を出たら、そのまま直進していただき、太閤通南口から駅を出てください。

【JR線・あおなみ線以外をお使いの方】
⑴ 銀時計へ向かいます
当オフィスに一番近い出口は、太閤通南口ですので、改札を出たらまず、銀時計へ向かってください。

⑵ 太閤通南口への通路を進みます
銀時計に着いたら、ギフトキオスクのある方向に進むと、名古屋・驛麺通りの入口が見えます。
その右隣りの通路が太閤通南口への通路ですので、その通路へ進んでください。

⑶ 太閤通南口から駅を出ます
通路を抜けると、名古屋うまいもん通り太閤通口の入口に着きます。
その状態で右を向くと、太閤通南口がありますので、そちらから駅を出てください。

2 横断歩道を渡って直進します
太閤通南口から駅を出たら、横断歩道を渡り、カフェ・ド・クリエ駅西口店を左手にそのまま直進します。
そうすると、正面にセブンイレブンの見える交差点に着きます。



3 横断歩道を渡って左に曲がります
横断歩道を渡り、セブンイレブンの正面で左折した後、そのまま直進してください。
正面にミニミニのある交差点があります。


4 オフィスに到着です
【名古屋オフィスの場合】
そのまま、横断歩道を渡ります。
ミニミニと同じビルの4階に当オフィスがありますので、ビルの右側にある入口からお入りください。
その後、エレベーターで4階までお越しください。

【本部オフィスの場合】
交差点の横断歩道を渡らずに右に曲がり、そのまま直進します。
すき家名駅西店を右手に通り過ぎると、ローソン椿町店の手前に「West Point1413」と書かれた緑の入口が見えます。
そちらの入口から当オフィスへお越しいただけますので、エレベーターで7階までお越しください。



名古屋オフィス・本部オフィスへの行き方
名古屋駅からの行き方です。写真付きで分かりやすいかと思いますので、お越しになる際は、こちらを参考にしていただければと思います。
栄駅から栄オフィスへのアクセスについて
1 中改札口から改札を出ます
当オフィスは、松坂屋名古屋店の中にあるため、最寄りの出口に行きやすい中改札口から出てください。

2 16番出口へ向かいます
16番出口が一番松坂屋に近い出口ですので、案内に従って、16番出口まで進んでください。


3 16番出口から地上へ出ます
「出口16」という黄色の案内が見えたら、横にある階段を上って地上へ出てください。

4 三越を右手にして直進します
地上に出ると、右手に名古屋栄三越が見えますので、そちらを右手にしたまま、直進します。

5 松坂屋名古屋店本館に到着です
16番出口を出てから横断歩道を3つ渡ると、松坂屋名古屋店本館に到着します。
当オフィスは、本館の7階にありますので、エレベーターなどで7階までお越しください。

近隣オフィスへの行き方
近隣にある私たちの他のオフィスへの行き方をご紹介しています。名古屋市内に複数のオフィスを設けていますので、お近くのオフィスをご確認ください。
矢場町駅から栄オフィスへのアクセスについて
1 1・5・6番出口側の改札から出ます
当オフィスは、松坂屋の店内にあるため、矢場町駅からお越しいただくには、1・5・6番出口側の改札を出てください。

2 Matsuzakayaと書かれた通路を進みます
改札口を出たら、右手にMatsuzakayaと書かれた看板が見えます。
そちらの通路を道なりに進んでください。

3 松坂屋の南館入口へ入ります
通路を進んでいくと、左手に松坂屋名古屋店の南館入口が見えてきます。
当オフィスがあるのは本館ですが、こちらの南館の入口からお越しいただけますので、南館へ入ってください。

4 本館への連絡通路を進みます
南館に入ると、すぐ右手にエレベーターのある通路があります。
こちらの通路を進んだ先に本館への連絡通路があり、そちらから本館に行くことができます。
通路を進んでいただき、当オフィスがある7階までお越しください。
電車でお越しいただきやすい事務所です
お読みいただくと分かるように、駅からのアクセスは良好で、電車でお越しいただきやすいかと思います。駐車場もありますので、お車での来所も可能です。
相続のご相談をお考えの方へ
1 相続手続きには期限があるものもある

相続手続きの中には、3か月や4か月以内という比較的短い期間に手続きを行わなくてはならないものが存在します。
期限が存在する手続きについて、万一、期限を徒過してしまうと、無申告加算税や延滞税等の税金がかかったり、その手続き自体が期限切れで行えなくなったりすることもあります。
そのため、相続に関しては、手遅れになる前に、まずは専門家にご相談されることをおすすめします。
専門家に相談するための費用が気になる方は、まずは無料相談を利用されるとよいかと思います。
2 ご相談の流れ
私たちは、一人でも多くの方にご相談をしていただきたく、相続に関して原則無料で相談を実施しております。
また、相続では複数の分野の知識が必要になることから、相続を得意とする弁護士や税理士等が必要に応じて連携もしています。
まずはお気軽にご相談いただければと思います。
ご相談までの流れとしては、以下のとおりです。
①フリーダイヤルにお電話いただくか、メール等でお問い合わせください。
②お問い合わせいただいた際、受付担当から関係者様のお名前やご相談の簡単な概要等をお伺いします。
③その後、弁護士や税理士等から、日程調整のご連絡を差し上げます。
④日程が決まりましたら、実際にご相談となります。
実際のご相談の方法として、事務所にお越しいただいて対面での相談だけでなく、電話やテレビ電話によるリモートでのご相談も実施しております。
3 相談の際に持って行った方が良いもの
相続のご相談の際は、運転免許証等の身分証の他に、可能であれば、通帳や固定資産税の通知など、相続財産が分かる資料や、戸籍謄本などの相続関係が分かる書類をお持ちください。
また、ご相談の内容をまとめたメモや相続関係図もお持ちいただけましたら、相談がスムーズに進みます。
もちろん、このような書類がなくともご相談自体は可能ですので、まずは、ご連絡ください。
4 手遅れになる前に早めのご相談を
繰り返しになりますが、相続手続きには期限があるものも存在し、中には、期限が切れてからご相談に来られる方もいらっしゃいます。
しかし、期限が切れてしまった相続手続きについては、専門家であっても、法的に対応が難しい案件もあり、お力になれない場合もあります。
そのため、相続でお悩みの方やご不安な方は、一度、相続の無料相談を活用し、お早めにご相談いただくことをおすすめします。
遺留分を請求したいとお考えの方へ
1 遺留分の請求には期限があります

遺留分の請求は、最短1年以内にしないと、時効により請求が認められなくなる場合があります。
もしくは、故人が亡くなった時から、10年を経過しても、遺留分の請求が認められなくなる場合があります。
万が一、遺留分が侵害されていそうな場合には、請求の具体的な金額が分かっていなくとも、すぐに請求した方がよいと思います。
また、たとえ遺言の無効を主張していた場合であっても、1年の期限内に遺留分の請求だけはしておいた方がよいでしょう。
なぜなら、仮に遺言が有効になった場合を想定すると、有効・無効を争っている間に1年の期限も過ぎてしまい、結果として遺留分さえも認められなくなるケースがあるためです。
なお、仮に遺留分の請求を行った場合でも、5年以内に訴訟等の手続きを行わないと、時効により、請求が認められなくなる場合もありますので注意が必要です。
2 遺留分とは
そもそも、遺留分とは、一定の相続人に保障された最低限度の相続の権利のことをいいます。
遺留分が認められる一定の相続人とは、故人の子や養子、両親等です。
他方、故人の兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合、彼らには遺留分は認められません。
また、遺留分が認められる場合として、遺言等の内容や故人から相続人等への生前贈与の内容、金額が不公平な場合に認められます。
遺言や生前贈与等が存在しない場合、遺留分の請求はできませんので注意が必要です。
遺言がない場合は、相続人間で遺産分割協議をし、遺産をどのように分けるかを決めることになります。
3 まずは遺留分に強い専門家に相談を
このように、遺留分の請求には期限があるため、できる限り早めに、請求を行う必要があります。
また、遺留分の請求を専門家に依頼する場合、どの専門家に依頼するかによって、認められる金額や解決までの期間が異なることがあります。
実際、遺留分に詳しくない専門家に依頼した結果、本来請求できる額よりも、かなり低めの金額しかもらえなかったというケースもあります。
そのため、遺留分の請求をお考えの方は、なるべく早めに、遺留分に強い専門家にご相談されることをおすすめします。
相続人の調査は専門家へ
1 相続人の調査は手間がかかる

相続の手続きなどにおいては、相続人の調査をすることが必要です。
相続人の調査は、市町村から戸籍を取得して行うことになります。
基本的には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍が必要になりますので、亡くなった方が、婚姻や離婚、養子縁組、転籍などによって本籍地を移転されていれば、その分、必要な戸籍の数が増えていきます。
また、相続人それぞれが存命であることを確認するために、各相続人の現在の戸籍も必要になります。
相続人が子どもだけであればまだよいのですが、子どもが全員先に亡くなっている場合には、代襲相続人となる孫がいないのか、またはすべての代襲相続人が誰であるのかを確認するために、子どもそれぞれの出生から死亡までの戸籍も必要となります。
相続人に子どもまたはその代襲相続人がいないということになれば、亡くなった方の両親らが相続人になりますし、その両親らも先に亡くなっているのであれば、兄弟姉妹またはその代襲相続人が相続人となり、必要な戸籍はさらに増えていきます。
このように、ケースによっては、、相続人の調査に手間と時間がかかります。
なお、相続人の調査が必要になる場面には、上記のような相続手続きだけではなく、借金の返済を請求する相手が亡くなったために、その相続人を調査しなければならないという場面もあると考えられます。
2 弁護士に依頼すれば相続人の調査をしてもらえる
弁護士には、職務に必要な限りで、戸籍等を請求する権限が認められています。
そのため、弁護士に依頼して、相続人の調査をしてもらうこともできます。
上記のとおり、必要な戸籍の取得には非常に手間と時間がかかる場合があるのですが、戸籍の取得に慣れている弁護士は、戸籍の取得に必要な手間と時間を省くことができますし、より効率的に戸籍を取得していく方法を知っています。
また、戸籍の内容の確認はある程度の知識がないと、せっかく必要な戸籍を集めることができても内容を正しく理解できないのですが、これができていないことで相続人を勘違いしてしまうなどの事態となってしまうと大変です。
弁護士は戸籍の内容を読み解くのに慣れていますので、相続人が誰であるのかを誤ってしまうという心配も必要ありません。
そのため、相続人を調査する場合には、弁護士に依頼することも検討するのがよいかと思います。
相続について弁護士に相談するタイミング
1 ご生前の場合

⑴ 認知症になる前に相談することが重要
相続についてご生前に様々な対策をとりたいと考えていても、本人が認知症を発症し、判断能力が減退してしまうと、法的な対策がとれなくなってしまいます。
軽度な認知症であれば、内容によっては遺言書を作成することもできますが、判断能力が低下した状態で判断した内容が適切かはご本人にも分からなくなりますし、他の相続人などから遺言書の効力を争われるおそれもでてきます。
そのため、生前から相続対策をとりたいとお考えの方は、認知症を発症する前に弁護士に相談されるようにしてください。
すでに認知症を発症されている場合には、より法的に慎重な判断が必要になりますから、弁護士から必要なアドバイスを受けたうえで、対策をされるようにしてください。
⑵ 遺言を作成する前に相談しましょう
最近では、信託銀行等の金融機関、民間の団体もご生前の相続対策の相談を受け付けているケースがあるようです。
無料サービスなどで遺言書の作成アドバイスを行っている団体もあるようです。
しかし、信託銀行の中には、遺言書の作成を弁護士等の国家資格を持った資格者が行うのではなく、財務コンサルタント等の銀行内部の職員が作成しているところもあるようです。
そのような職員が、必ずしも相続についての専門的な知識を持っているわけではなく、さまざまな法律上の問題、税務上の問題について適切なアドバイスができるわけではないと考えられますので、注意されてください。
遺言書は一度作成をしても、何度でも作成し直すことができるものの、一度、金融機関に遺言書を作成してもらって遺言書作成報酬等を支払うと、作成し直すことになったとしても、報酬の全額が返金されないところが多いでしょう。
弁護士のように、「遺言書があっても裁判になるケース」を知っている専門家であれば、どのような遺言書が紛争につながりやすく、作ってはならないものなのか熟知していますが、そうでない方はなかなかそのような観点から遺言書を作ることは難しいといえるでしょう。
そのため、遺言書を作成する前から、遺言に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。
2 亡くなった後の場合
⑴ 亡くなってから3か月経過する前に弁護士にご相談を
相続放棄をするためには、自らが相続人となったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述の受理申立てをする必要があります。
相続放棄をお考えの場合は、この期間を経過してしまうと相続放棄できなくなってしまうのが原則です。
家のローンや経営している会社の借り入れ等、亡くなった方に借金があった場合や借金があるかもしれない場合には、速やかに弁護士に相談し、借金の調査や相続放棄の手続きをとってもらうべきです。
⑵ 遺産分割前に弁護士にご相談を
法律では、相続人が遺産に関する取り分を一定程度決めており、これを法定相続分といいます。
しかし、遺産分割協議では、法定相続分以上に遺産の取得を請求されることはしばしばありますし、そもそも法定相続分の相続内容が明らかではないということもあります。
相続というのは、人が何度も経験するものではありませんし、それぞれの事情によって、どのように対応するのが適切なのかが分からないことも多いでしょう。
乏しい知識のまま手続きを進めてしまうと、誤解などによって、相続人間でのトラブルを招きかねません。
そのため、自らの相続分としてどの程度の主張が可能なのか、どのように協議を進めていけばよいのか、予想される相手方からの主張にはどのように反論をすればいいのかなどについて、予め弁護士に相談されることをお勧めします。
⑶ 遺産分割協議で決着がつかなかった場合は弁護士にご相談を
遺産の分け方を話し合う場である遺産分割協議において、当事者同士で決着がつかなかった場合、弁護士に相続人の間に入ってもらって交渉してもらう必要があります。
相続人の代理人として活動することができるのは弁護士だけですので、この場合は、速やかに遺産分割に詳しい弁護士にご相談ください。
調停や審判などの裁判手続きになってしまった場合にも、法的な主張を適切にしていく必要がありますので、弁護士にご相談ください。
相続問題について専門家に相談すべきケース
1 遺言書を作りたいと考えている場合

お早めに専門家にご相談されることをおすすめします。
特に、ご年齢が80歳を過ぎていますと、せっかく遺言書を残したにもかかわらず、認知症等が進んでいて遺言能力がなかった等と後から争われる可能性があります。
遺言無効確認訴訟についても詳しい弁護士であれば、どのような遺言書であれば争いを避けることができるのか理解していますので、ご相談されるとよいかと思います。
2 相続放棄をお考えの場合
すぐに専門家にご相談されることをおすすめします。
相続放棄は、被相続人が亡くなり相続の開始があったことを知ったときから、3か月以内に家庭裁判所に申述しなければならないという時間制限があります。
また、上記の期限を過ぎていなくても、被相続人の遺品を処分した、被相続人の賃貸マンションを解約した等の行為を行っている場合は、法定単純承認事由に該当する行為を行っているとして相続放棄が認められなくなってしまうおそれもあります。
時間が経てば経つほど、法定単純承認事由に該当する行為を行う可能性も高くなりますので、すぐに相続放棄に詳しい弁護士にご相談ください。
3 遺産分割をお考えの場合
できるだけお早めに専門家にご相談ください。
遺産分割を終え、遺産分割協議書を作成しなければ、相続税申告、被相続人の預貯金の解約・払戻し、被相続人の不動産登記の名義変更等を行うことができません。
遺産の中に不動産や株式等の有価証券が含まれている場合は、亡くなった後の時間経過に伴い、価額が変動しますので、早めに遺産分割をまとめるべきです。
なお、依頼者に代わって、他の相続人と交渉することができるのは、専門家の中でも弁護士しかできませんので、早めに遺産分割に詳しい弁護士にご相談ください。
4 遺留分侵害額請求をお考えの場合
すぐに専門家にご相談ください。
遺言によって、相続人の遺留分が侵害されている場合、遺留分侵害額請求を行うことができます。
ただ、遺留分侵害額請求は、原則として遺留分の侵害を知ってから1年以内でなければできません。
遺留分を侵害している方に対して早急に請求しなければ、消滅時効が成立してしまい、何も請求できなくなってしまう可能性がありますので、すぐに遺留分侵害額請求に詳しい弁護士にご相談ください。
相続の生前対策をお考えの方へ
1 遺言書の作成

相続の生前対策で重要なのは、やはり遺言書の作成です。
遺言書を作成しておけば、ご本人が亡くなったときにどのように財産を相続させるかを、基本的には自由に決めることができます。
そのことは、相続人にとっても、遺産分割協議をする労力を省くことができるなどのメリットがあり、その効果は非常に大きいかと思います。
また、一般に遺言書を作成しておいた方が、相続開始後、相続人間でトラブルになる可能性が低くなります。
そのため、相続の生前対策において遺言書の作成は必須であるといえます。
2 死後事務委任契約
相続の生前対策として、自らが亡くなったときに、死後の事務を委任する死後事務委任契約を結ぶケースも増えてきています。
死後事務の内容としては、葬儀や納骨の他、役所への各種の届出、関係者への通知などの事務があります。
もちろん、ご親族でこれらの手続きを行ってくれる方がいれば問題ございませんが、親族と疎遠な方や親族がいらっしゃらない方などは、どなたかに各種手続きを依頼しておかないと、適切な手続きがされない可能性があります。
これらの死後事務について、どこまでの内容を専門家に依頼するのかについては、事前に専門家と入念に打ち合わせる必要があります。
3 相続税対策
相続の生前対策として、相続税への対策をしておくことも非常に重要です。
そもそも相続税がかかるのかどうかや、相続税がかかるとすれば、いくらかかるのかを把握することが、まずは大事です。
その上で、どのような相続の内容にすれば相続税を支払う額が少なくなるのか、相続人の相続税の納税資金をどのように用意するのかといったことを検討することになります。
相続での分け方を検討する他に、不動産の購入や売却、生命保険の加入などの手段を検討することになります。
注意点として、不動産の購入や売却、生命保険に関しては、適切なところに相談しないと、相続税対策にもならず、損をしてしまう場合やトラブルに発展する場合があります。
そのため、相続税対策をご相談する場合は、不動産会社や保険会社だけでなく、必ず、相続税に強い税理士にご相談されることをおすすめします。
4 相談するタイミング
相続の生前対策については、なるべく早いタイミングで相談をしてほしいと思います。
なぜなら、自分の相続がいつ生じてしまうかは分かりませんし、なるべく早いタイミングで対策をすることが、様々な対策の手段を確保することにもつながるからです。
例えば、相続税対策については、一般に対策が早ければ早いほど、効果が高まります。
また、遺言書で説明しますと、字が書けるのであれば自筆証書遺言の作成もできますが、自分で字が書けない状態になってしまえばこの手段での作成はできなくなってしまいますし、そもそも遺言書を作成する意思能力がなくなってしまえば、遺言書を作成できなくなってしまいます。
このようなことがないよう、なるべくお早めの相談をおすすめします。
不動産評価に強い専門家に相談すべき理由
1 遺産分割協議や遺留分侵害額請求の場面

弁護士が扱う相続の案件では、相続財産に不動産が含まれていることが多く、むしろ不動産がないことの方が珍しいといえます。
不動産の評価額としては、土地については「一物四価」という言葉があるくらいで、すべての事案で適用される一定の評価額があるわけではありません。
例えば、上に書いた「四価」とは、時価(実勢価格)、公示価格、路線価(相続税評価額)、固定資産税評価額のことを指しますが、どの場面でどの価格を採用したり参照したりすべきなのかは事案によります。
遺産分割協議の場面で、不動産を取得したいという側にとっては、不動産の評価額が低い方が有利ですから、どのような評価方法をとれば不動産の評価額を下げられるかという視点から不動産の評価をします。
他方で、不動産の代償金を受け取りたいという側にとっては、不動産の評価額を上げるためにはどのような評価方法をとればよいのかという視点から検討することになります。
遺留分侵害額請求の場面でも、その不動産を取得している方にとってはその不動産の評価額は低い方が有利でしょうし、相手方が取得している不動産については、高く評価することが有利になります。
どのような点を主張すれば、不動産の増価や減価の要素となるのかについては、不動産の深い知識が必要ですので、不動産評価に詳しい専門家に依頼する必要があります。
2 相続税申告の場面
相続税の申告においても、相続財産の中に不動産が含まれている場合には、これを評価する必要があります。
相続税において不動産をどのように評価するのかは、国税庁が出している財産評価基準をもとに評価することが一般的です。
相続税を適正に申告しようとすれば、財産評価基準に従った評価方法をしっかりと理解して不動産の評価をする必要があるのですが、すべての税理士がこれを十分に理解しているとは限りません。
というのも、すべての税理士が相続税や不動産を対象とする贈与税の申告業務を普段から行っているわけではないことから、不動産の評価方法を十分に理解していない税理士もいるのです。
そのような税理士に相続税申告を依頼してしまうと、適正な不動産の評価がなされていなかったり、本来は様々な減価要素があるにもかかわらず、これを見逃してしまったりして、税金を払い過ぎてしまうことにもなりかねないため、注意しなければなりません。
遺産分割についてお悩みの方へ
1 遺産分割についての悩みの内容

遺産分割についてのお悩みには様々なものがあります。
例えば、相続人の一部と連絡が取れずに困っているというお悩みであったり、他の相続人から不当な要求をされているというお悩みであったり、他の相続人と連絡を取りたくないというご要望であったりします。
このように遺産分割についてのお悩みは様々であるとは思いますが、以下では、その代表的なものについて、どのように進めていけばよいのかを説明していきます。
2 相続人の一部と連絡が取れない場合
遺産分割協議では、相続人全員で分割内容を決める必要があります。
相続手続きを進める上で必要な書類としては、少なくとも、相続人全員の遺産分割協議書と印鑑登録証明書が一般的です。
相続人の一部と疎遠で、音信が不通である場合にも、その相続人の戸籍の附票などから現在の住民票上の住所を把握することができますので、その住所に遺産分割協議についての連絡をすることができます。
それでもその相続人と連絡を取ることができない場合には、法的な手続きを取る必要があります。
この場合の手続きとしては、遺産分割調停の申立てであることが一般的です。
遺産分割調停とは、相続人同士の遺産分割の話合いを裁判所で行う手続きです。
ここで、連絡が取れないのであれば、調停ではなく、裁判所が分割内容を決定する審判手続きを申し立てるべきとも考えられます。
しかし、連絡の取れない相続人が、裁判所からの連絡があれば、これに応答するという可能性もあることから、このようなケースでも、まずは遺産分割調停を申し立てるという手段がとられることが多いといえます。
ここで、相手方の相続人が調停に参加すれば調停の中で手続きを進め、調停に参加しなければ、基本的に、審判によって遺産分割内容が決められることになります。
3 分割内容が決まらない場合
遺産分割協議の中で、相続人間の分割内容が決まらないという場合があります。
相続人の一部が自らの法定相続分を超える権利を主張していたり、遺産の内容からするとどうしてもそれぞれの相続分に従った分割内容を決めることが困難だったりする場合があります。
前者の例としては、相続人の一部が、自らは被相続人の面倒を看てきており、被相続人との関係も深かったため、他の相続人よりも多くの財産を相続できるはずだという主張をしてくる例があります。
このような主張は、法律上は、寄与分の主張として位置づけられ得るものではあるのですが、寄与分として認められるためには非常の多くのハードルがあるため、このような主張を通すことは容易ではないと考えていただいた方がよいといえます。
どのような場合であればこれらの主張が認められ、これらの主張を裁判所に認めてもらうための証拠があるかどうかといった視点を持って、遺産分割協議を進めていく必要があります。
後者の例としては、例えば、遺産のほとんどが自宅であり、預貯金がほとんど無いという場合があります。
自宅に相続人の一部が住んでいる場合や、自宅の土地の上に相続人の所有する家屋が建っている場合には、不動産を相続人同士で共有にしてしまうと、住んでいない相続人にとっては何のメリットも無い財産となってしまいますし、管理の上でも望ましい状況にあるとはいえません。
そのため、当該不動産を取得する相続人が、その不動産を取得する代わりに代償金を支払うという内容の遺産分割をすることが望ましいのですが、相続財産に預貯金が無いため、これによって調整をすることができません。
相続人にもともと資金があれば、これから代償金を支払うということで問題は無いのですが、多額の不動産の価値に相当する金銭を用意できないという場合も多いといえます。
そのような場合には、不動産を売却して、その売却金を相続人で分けるという方法しか無くなってしまうのですが、住んでいる相続人にとっては住む場所を奪われるという結果になってしまうため、そのような内容の合意をすることも困難です。
後者のようなケースが遺産分割では最も困難な例の一つなのですが、代償金の額や分割方法などでの調整がつかない場合には、法的な手続きも含めて、対応が必要になってしまうケースであるといえます。
4 他の相続人と連絡を取りたくない場合
遺産分割協議は、親族間で行うものですから、それぞれの家族の経緯からすると、感情的な問題から連絡を取りたくないという場合もしばしばあります。
とはいえ、自らが連絡を取らないままでいれば、相続手続きは終わることはありませんし、それが望ましい状況であるとはいえません。
相続放棄の手続きをとれば、相続手続きから解放されることができますし、これは放棄をする方自身で決められることではあります。
ですが、事実上、他の相続人とまったく連絡を取らなくても済むかどうかは分かりませんし、相続放棄をすることが感情的に受け入れられないこともあるでしょう。
そのような場合には、弁護士に遺産分割協議を依頼し、自らの代理人として活動してもらうことも検討してみてください。
弁護士に遺産分割協議の依頼をすれば、相続についての方針は依頼者が決定することになりますが、その決定をするために弁護士からのアドバイスを受けることができますし、他の相続人との交渉は弁護士にしてもらうことができます。
各専門家が協力できることの強み
1 相続では様々な専門家が関わる

相続の手続きと一言でいっても、その内容は多岐にわたりますので、関わる専門家も様々です。
例えば、亡くなった方が遺言書を作成しないまま亡くなったとします。
そうすると、相続人が複数いる場合には、その相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。
遺産分割協議にあたっては、まず相続人が誰かということを調べた後に、遺産分割の対象となる遺産としてどのような財産があるかを調べる必要があります。
この際、相続人が誰かを調べるためには戸籍を取得する必要がありますが、この作業を専門家に依頼する場合の依頼先は、弁護士や司法書士です。
遺産分割の対象となる財産を調べるのも弁護士や司法書士です。
また、亡くなった方の相続人が、準確定申告や相続税の申告を行わなければならない場合があります。
この税金関係の業務を行っているのは、税理士です。
遺産分割協議で揉めてしまった場合に、相続人の代理人として活動し、遺産分割協議を解決するためには、弁護士に依頼する必要があります。
また、相続財産の不動産を売却しようとなった場合には、不動産仲介業者の宅地建物取引士が仲介して行います。
このように、相続では様々な専門家が関わっています。
2 各専門家が協力できることの強み
このように、相続においては様々な専門家が関わっていますが、その専門家同士でしっかりとした協力関係がないと手続きがスムーズに進まないことがあります。
例えば、相続財産を調査する過程で、それぞれの金融機関での手続きを行うことがありますが、相続税の申告において必要な書類をこの際に取得していないために、再度、金融機関から書類を取り寄せる必要が生じてしまい、二度手間となってしまうことがあります。
このようなことは、それぞれの専門家が他の業務分野のことを知らないために生じるものです。
ここで、各専門家が協力できており、相続財産調査の過程で、相続税申告に必要な書類を取得していれば、上記のような手間を省くことができます。
このように、単に手間が増えるだけであればよいのですが、遺産分割協議において税金のことをまったく考えていないために、トラブルになることもあります。
例えば、遺産分割協議をして、せっかくまとまったにもかかわらず、実は、他の分割内容にしていれば相続税で効果的な控除が受けられるのに、それを考慮して遺産分割をしていなかったことが判明し、トラブルになるというようなケースです。
このようなことも、遺産分割協議と相続税のことの両方を熟知していれば防げたトラブルであるといえます。
これらのトラブルを防ぐためには、例えば、弁護士と税理士の両方の資格を持つ専門家や、弁護士業務と税理士業務の連携がしっかりしている事務所を選ぶ必要があります。
相続の相談先の選び方
1 相続に関する相談先

相続は、どこのご家庭にも発生しうる身近なものですが、様々な法律や税金に関する問題が複雑に絡み合う分野であるため、慎重に対応しなければ、想定していなかった税金が課せられるなど、思わぬ不利益が発生するおそれがあります。
そのため、相続については専門家に相談しながら手続きを進めることが大切です。
相続の相談をする場合は、弁護士や税理士などの国家資格を有している専門家に相談されることをおすすめします。
近年は信託銀行等でも相続の相談を取り扱っていることがありますが、銀行の担当者が国家資格を有しているとは限りませんので、必ずしも責任を持ったアドバイスができるとはいえません。
2 相続の相談は相続に強い専門家へ
また、国家資格を有していても、必ずしもその有資格者が相続に詳しいとは限りません。
法律や税金の分野において、相続は数多くある分野のうちの一つに過ぎないため、相続をほとんど扱ったことがないという有資格者もいます。
そのため、相続について相談する場合は、国家資格を有していて、かつ相続に強い専門家に相談すべきです。
3 相続に強い専門家の特徴
医療の世界でいうと、脳神経外科の医師が脳の外科手術に精通している理由は、その分野に特化して、脳の外科手術を多く手がけているためです。
相続でも同じように、相続に強い専門家は、相続分野を集中的に取り扱い、多くの実績を積むことで、その分野に精通しています。
例えば、相続は様々な税金が深く関わる分野のため、税金の計算や手続きを間違えてしまうと、余計に税金を支払わなければならないといった事態になるおそれがあります。
相続の実績を多く積み重ねた専門家であれば、税金についても深く関わることが多いため、このような間違いを未然に防ぎながら手続きを進めることができます。
相続の相談をする際は、このように相続の取扱実績を多数持つ専門家を選ばれることをおすすめいたします。
4 相続の相談は早くすることが大切です
相続の相談は、大きく分けて「生前の対策の相談」と「相続発生後の相談」があります。
生前の対策については、例えば、相談者の方が認知症等になってしまうと対策を行うのが難しくなってしまうことがあります。
相続発生後の手続きについても、法律で期限が定められているものもありますし、自分で進めていく中で思わぬ失敗をしてしまうこともあります。
そのため、相続についての相談はとにかく早めにすることが大切です。
専門家に相談する際の流れ
1 どのような内容の相談をするかを確認する

専門家に相談する場合、まずはおおまかにどのような相談をしたいのかを確認しておくことがおすすめです。
例えば、相続に関する相談をしたいという場合には、それは遺言書の作成や相続税の対策などの生前の相続対策についてなのか、遺産分割協議や相続税の申告など相続が発生した後の手続きについてなのかといったことを、しっかりと確認しておくとよいかと思います。
それによって、法律の分野の相談であるのか、税金の分野での相談であるのかが変わってきますし、専門家に相談する際にも、スムーズに相談内容を伝えることができます。
2 その分野に強い専門家を探す
相談の大まかな内容が決まったら、その分野に強い専門家を探す必要があります。
情報の収集方法は様々ですが、今の時代はインターネットを使ってその分野に強い専門家を探すことが多くなっています。
もちろん、知り合いの紹介で専門家を選ぶという方法もありますが、紹介された専門家がその分野に強いとはいえない場合もあることから、できればご自身で探していただいた方が無難だといえます。
例えば、相続を扱っている弁護士は多くいますが、相続を集中的に扱っている弁護士は多くいるわけではありませんし、そのような弁護士とそうでない弁護士の間では、相続に関する知識と経験に大きな差があることがあります。
相続税に関しても同様で、すべての税理士が相続税について精通しているわけではありませんので、なるべく相続税に強い税理士を探していただき、相続税に関する相談をしていただきたいと思います。
3 事務所へ連絡を取って相談をする
相談をしたいという専門家が決まったら、事務所に連絡をします。
電話やメールなど、事務所のホームページを見れば、連絡先や連絡方法が分かります。
連絡をした後、事務所に直接訪れて相談をする場合が多いですが、事務所によっては、電話で相談をすることもできると思います。
事務所に訪れて相談をする場合には、相談の日時、事務所が複数ある場合には場所の希望を伝えた上で、専門家と日程を調整して、相談をすることとなります。
この際に必要な書類は、事務所から案内されるかと思います。
4 相談をした後に依頼するか検討する
相談をした後、専門家に相談事項を依頼するかどうかを検討します。
手続きの進め方や費用の見積もりについては、相談の際に提示されるかと思いますので、これらを踏まえて、依頼するかどうかを検討します。
依頼をするかどうかを検討する際には、費用が納得できるものであるかどうかや、手続きの進め方についてしっかりと説明してくれたかどうか、親身に相談に乗ってくれたかどうかなどを考慮して決めるようにしてください。
多くの専門家がいますから、複数の事務所に相談をしていただいて、その中から依頼する専門家を選ぶということもよいと思います。
遺言書についてお悩みの方へ
1 遺言書はできる限り早めに作成した方がよい

遺言書を書かなかったがために、残された相続人同士で泥沼の紛争になることがあります。
実際、これまで仲が良かった兄弟が、遺言書がなかったために、数年経っても遺産の分け方が決まらず、それ以降、絶縁状態になってしまったケースもあります。
他方、遺言書は、一度作ったとしても、何度でも内容を変更することができます。
そのため、残される相続人のためにも、できる限り早めに、簡単な内容でも構いませんので、遺言書を作られることをおすすめします。
2 遺言書についてのご本人以外からのご相談
法律事務所に遺言書についてのご相談があるケースには、2つの種類があります。
一つは、自らの遺言書を書きたいという方からのご相談です。
もう一つは、家族に遺言書を書いてほしいという方からのご相談です。
ご本人は、「自分が亡くなった後のことについては家族で決めてくれたらいい」「相続のことは子どもたちに話しているので、子どもたちが揉めるはずはない」「そもそも、遺言書なんてどうやって書いたらいいのか分からない」というようにお考えかもしれません。
しかし、きちんとした遺言書が残っていれば、基本的に、家族はどのように相続をするのかについて話し合う必要はなくなるため、遺言書があると非常に安心されるかと思います。
他方、家族からすると、親や配偶者の相続のことについて悩んでいて、ご本人に遺言書を書いてほしいと思っていたとしても、そのような話を持ちかけることは気が引けるという方も多くいらっしゃいます。
そのような家族の方から、「遺言書を書いてくれたら、このようなメリットがある」ということをご本人に伝えたいため、遺言書について聞きたいというご相談も多いのです。
3 遺言の内容は慎重に検討した方がよい
ご本人が遺言書を作成しようという気持ちになったとして、遺言書を書いてもらうというだけでも家族には大きなメリットがあると考えられますが、せっかく作成した遺言書が、「実は無効だった」ということになると、遺言書を書いた意味がありません。
法的に有効な遺言書であるためには法律上の要件を満たしている必要がありますので、これを備えていることが必要です。
例えば、手書きの遺言書の場合、日付を具体的に記載する必要があり、「令和5年1月吉日」と書いてしまうと、それだけで遺言書が無効になってしまいます。
これに加えて、遺言書の内容がどのようなものかも非常に大事です。
例えば、遺言書の内容が遺言者の思ったとおりに書かれているものだったとしても、専門家から見ると、相続の紛争を招きかねないような内容であったり、法律上の手続きを進めることができない内容だったり、税金のことが考慮されていない内容だったりすることがあります。
財産を受け取る側の家族からすると、遺言書の内容どおりの相続をした場合に非常に困る結果となるのであれば、結局、家族の間で話し合って、遺言書とは異なる合意をしなければなりません。
このような結果となってしまっては、せっかく遺言書を書いたご本人にとっても本意ではなかったということになるかと思います。
そのため、遺言書を書く際には、専門家からその内容についてもしっかりとアドバイスを受けながら、法律面だけでなく税金面も考慮して、内容を慎重に検討する必要があります。
4 相続に詳しい専門家に相談した方がよい
今、世間では、遺言書を書くことについてのメリットが認識されているため、様々な書籍が出版され、セミナーも開催されており、政府でも積極的にこれを後押しする政策がとられています。
ただ、どのような遺言書の内容が最適なのかは、ご本人の具体的な状況や考え方によりますし、書籍やセミナーだけでしっかりと分かるようになるわけではありません。
ご本人の遺言書を書こうと思った具体的な動機や、ご本人の資産の内容や家族との関係、ご本人の年齢や将来に対する計画などは千差万別ですので、思ったとおりの遺言書とするためには、内容を細かく検討しなければなりません。
また、ご本人が気づいていないことや想定していないことについても、指摘してもらう必要があります。
実際に、どのような遺言書だと、家族が相続で揉めることになるのかについては、そのような事例に多く接している専門家でないと分からない面があります。
そのため、遺言書を作成するのであれば、相続に詳しい専門家に相談した方がよいといえます。
遺言書を書く際に最も気を付けなければならないのは、遺言書によって家族が揉めてしまうような内容にしないことだと考えられ、相続を得意とする専門家であればそのような事例に多く接していますので、相談をするのに適任であるといえます。
また、遺言においては、不動産の評価や名義変更についての知識、税金についての知識、不動産売却、保険契約についての知識などの幅広い知識が必要とされますし、これらの知識をもとに具体的な対応ができることも不可欠です。
遺言についてのご相談をされるのであれば、これらについても普段から研究を重ねており、その方に合った対策にも対応できる専門家に相談されることをおすすめします。
相続放棄をお考えの方へ
1 相続放棄をするかどうか検討する

相続人が相続をした場合には、遺産のプラスの財産とともに、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。
亡くなった方とは長期間にわたって疎遠であり、その財産を引き継ぎたくないという方や、他の相続人と関わりたくないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ただ、経済的なことだけを考えると、プラスの財産の方がマイナスの財産よりも多ければ相続をした方がよいですし、マイナスの財産の方が多ければ相続放棄をした方がよいと考えられます。
プラスの財産がどの程度あるかは、不動産、預貯金、株式などの有価証券など、それぞれの財産の性質に従って、調査をする必要があります。
亡くなった方の財産を管理していた人がいない場合や、そのような人がいてもその人から財産に関する情報を得られない場合には、どのような財産があるのかについて、自宅に残ったものなどを調べるなどして、調査をしなければなりません。
マイナスの財産の調べ方は、基本的に、信用情報機関への照会を行うことになりますが、不動産の登記内容で住宅ローンや保証債務の担保となっていないかを調べることも、マイナスの財産の調査方法として有用です。
ただし、特にマイナスの財産については、個人からの借入れについては痕跡が残っていないことも多く、プラスの財産やマイナスの財産のすべてを確実に把握することには限界があります。
相続を放棄するかどうかを検討する場合には、調査しきれていないマイナスの財産があるリスクも踏まえて、検討するとよいと思います。
2 家庭裁判所に相続放棄を申述する必要がある
相続する権利を放棄する場合には、家庭裁判所にその旨の申述をし、それを受理してもらうように申し立てる必要があります。
申立てをする家庭裁判所は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
相続放棄の申述の受理を申し立てる場合には、亡くなった方の最後の住所地が分かる住民票除票や戸籍の除附票、亡くなった方の現在戸籍や申立人の現在戸籍などを提出する必要があります。
ここで提出しなければならない書類は、申立てをする相続人が亡くなった方との関係でどのような立場にあるのかによって変わってきます。
相続を放棄したいという意思を持っていたとしても、放棄するという意思を表明しただけの場合や、相続の手続きをしなかったというだけの場合は相続をしたと扱われてしまうため、思わぬ不利益を受けることがあります。
ですので、裁判所での相続放棄の手続きは確実に行ってください。
3 相続放棄の申立てには期限がある
相続の放棄の申立てには、自らが相続人であることを知った日から3か月以内に行わなければならないという期限があります。
この期限を過ぎてしまうと、基本的に相続を放棄することは認められませんので、注意する必要があります。
2で書いたような書類を収集していると、場合によっては、3か月という期間はあっという間に過ぎてしまいますので、なるべく早めに対応することをおすすめします。
また、1で書いたような財産の調査を行っていると、3か月では間に合わないことがありますが、この場合には、家庭裁判所に対しこの期間を伸長してもらうように申し立てることができます。
ここで、亡くなった日から3か月以内に相続を放棄する旨を申し立てていれば、期間内に行っているため特に問題はありません。
しかし、何らかの事情で、亡くなった日から3か月過ぎた日に申立てをした場合には、自らが相続人であることを知った日が亡くなった日ではないということを説明する必要があります。
例えば、亡くなった方とはずっと疎遠であり、債権者からの通知によって自らが相続人であることを初めて知ったのであれば、債権者からの通知を資料として裁判所に提出するなどして、自らが相続人であることを知った日がその日であることを説明しなければなりません。
このような資料が手元に残っていれば、裁判所に提出して説明することができますが、このような資料も手元に無いのであれば、場合によっては、相続の権利を放棄する人が裁判所に出向いて、その旨を説明する必要がある場合もあります。
このような事態にならないように、相続放棄をする必要がある場合には、お早めに専門家に相談をしていただくことをおすすめします。
弁護士に依頼した場合の相続財産の調査方法
1 相続財産の調査をしなかった場合の落とし穴

相続財産の調査をしっかりとしていなかった場合、後日、大きなトラブルになることがあります。
例えば、亡くなった方に、実は多額の借金があったことが判明した場合はどうなるでしょうか。
プラスの相続財産があるということで相続をしたものの、それを上回るような多額の借金を引き継ぐことになってしまうのであれば、そもそも相続はせずに相続放棄をすべきであったということになります。
相続財産という言葉からは、ついついプラスの財産をイメージしてしまいがちですが、相続財産の中には借金のようなマイナスの財産も含まれますので、双方の財産の調査をすることが重要だといえます。
その他に、判明している相続財産だけを遺産分割の対象にして遺産分割協議をしていたものの、何十年も経った後に認識していなかった遺産が見つかり、そのときには当時の相続人の一人が認知症で判断能力を失っていたり、所在が不明になったりしたことで、遺産分割協議ができず、相続手続きができなくなってしまったということもあるかと思います。
このように、相続財産の調査をしっかりしていないと思わぬ落とし穴がある場合がありますので、相続財産の調査は十分にしておくことが必要となります。
専門家に相続財産調査を依頼することも検討してみるのがおすすめです。
2 弁護士による相続財産の調査の方法
⑴ 預貯金の取引履歴からの調査
親が亡くなったとして、親の遺産の詳細まで把握している子どもは多くはないのではないでしょうか。
親が加入している生命保険会社はどこなのか、株式は持っているのかなどは、なかなか分からないこともあります。
親が、終活などの一環として、自らの財産の内容をメモなどで残すということをしておいてくれるとよいのですが、そのようなものが無い場合には、相続財産を調査することが必要になります。
そのような場合、弁護士であれば、通帳や金融機関から取り寄せた預貯金の取引履歴を調べて、相続財産に関する手がかりを探します。
具体的には、預貯金の出入金の履歴から、普段のお金の流れを把握し、亡くなった方がどういった財産を所有していたのかを調べていきます。
例えば、亡くなった方が年金を受給していたはずなのに、そのような履歴が見つからないというような場合には、判明している以外の口座があると推測することができます。
⑵ 戸籍の内容からの調査
弁護士は、相続人の戸籍を取得し、亡くなった方や、その両親などの本籍地を調べ、その地域に先祖代々の不動産があるのではないかといった目星をつけて、不動産の調査をすることもあります。
具体的には、相続財産である不動産がある可能性のある市町村に対して、名寄帳などの書類の発行を依頼して、そこに不動産があるかどうかを調査します。
不動産があることが確認できたら、どのような内容の不動産であるのかを登記情報を取得することなどで把握します。
⑶ 様々な手がかりからの調査の方法
このように、弁護士は、どのような相続財産があるか分からない状態から、様々な方法で手がかりを見つけ、相続財産の調査をします。
弁護士は、市区町村、金融機関、証券会社等に情報開示請求を行い、相続財産の調査をしていきます。
借金の有無や内容を調べる方法としては、家に届いている通知や、通帳の履歴から目星をつけ、借金の情報を管理している業者や、信用情報機関に対して情報開示請求をして、借金の有無や内容の調査をします。
生命保険があったかどうかを調査する方法としては、生命保険協会に対する照会や、通帳の履歴を確認することで調査を行います。
3 相続財産の評価も大切
相続財産を見つけた後は、その財産がどのくらいの価値なのかを計算する必要もあります。
例えば、土地や建物などの不動産がどれくらいの価値があるのかを把握することも重要です。
不動産の額によっては、相続税の申告をする必要も出てきますし、遺産分割の協議の結果も変わってくるため、不動産の価額の評価も重要なポイントとなるのです。
弁護士は、固定資産税評価証明書などの書類を取り寄せて、不動産の固定資産税評価額を把握したり、路線価や不動産の査定額などを調べたりすることによって、不動産の評価をします。
相続のお悩みの種類
1 相続の悩み事の種類

相続のお悩みには、大きく分けて2つあります。
1つは、自分自身の相続について、あらかじめ対策を打っておく「生前対策のお悩み」です。
もう1つは、ご家族が亡くなり、「相続が発生した後のお悩み」です。
いずれのお悩みも、財産、税金、感情の対立など、様々なことを考慮しながら対応する必要があります。
ここでは、それぞれのお悩みに関してお話しいたします。
2 生前のお悩み
まず1つ目の生前対策において、一番大切なことは、残されたご家族が遺産をめぐって揉めないようにすることです。
遺産をめぐる争いを防ぐためには、遺言書を作成しておくことがもっとも基本的かつ有効な手段です。
遺言書が無ければ、相続人全員で遺産の分け方を話し合う必要がありますが、遺言書があれば、原則として遺言書どおりに遺産を分けることになります。
そのため、遺産の分け方を話し合う必要はなくなり、ご家族が揉めてしまうおそれを防ぐことができます。
もっとも、遺言書の書き方によっては、かえって揉め事を起こしてしまうこともあるので注意が必要です。
そのため、どういった遺言書が作成されてしまうと裁判などに発展してしまうのかということを熟知している専門家に相談することが大切です。
その他に生前対策として検討すべきことに、税金の問題があります。
相続の場面では、様々な税金が発生する可能性があるため、ご家族にはこれらの税金を支払えるだけの現金を残しておくように準備をしておかなければなりません。
また、生命保険の活用や生前贈与等、相続税対策の方法については、早めに始めれば始めるほど、その効果は高くなります。
そのため、税金に関してご不安な方は、早い段階で相続税等の税金に詳しい専門家にご相談された方が良いでしょう。
3 相続が発生した後のお悩み
相続が発生した後には、預貯金の解約や不動産の名義変更手続きなど、様々な手続きが必要です。
家族で遺産をめぐって争いになってしまった場合は、裁判所での手続きが必要になることもあります。
相続発生後のお悩みについては、高度な法律知識や、判例についての知識が必要になるため、すぐに相続の専門家に相談することが大切です。
また、相続手続きの中には、3か月や10か月、1年などの期限があるものも存在し、期限が過ぎてしまうと、本来請求できるものが請求できなかったり、延滞税や無申告加算税等のペナルティを課せられたりする場合があります。
そのため、まずは、専門家に相談することで、期限を徒過することがないようにしておくことが重要です。
4 相続を集中的に扱っている専門家に相談するのがおすすめです
生前対策も、相続が発生した後のお悩みも、相続に関する法律や、税金などの複数の分野が複雑に絡み合うこととなります。
そのため、相続を集中的に取り扱い、実績が豊富な専門家に相談することが大切です。
どの専門家に相談すればよいのか迷われた際は、相続問題をトータルサポートできる私たちにご相談ください。
お悩みをお伺いし、適切に対応できる専門家が問題解決に向けてサポートいたします。
また、相続の相談は原則無料で実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
相続の手続きを放置するデメリット
1 相続の手続きを放置すると様々なデメリットを負う可能性がある

相続の手続きを放置してしまうと、例えば、無申告加算税や延滞税等の税金を課せられたり、勝手に遺産を処分されてしまったり、いざ相続手続きを行おうと思っても、相続関係が複雑になりすぎて、解決まで多額の時間と費用が掛かるようになったりする場合がある等、様々なデメリットを負う可能性があります。
そもそも、相続手続きをするためは、相続人の確定に必要な戸籍を集め、相続財産の内容を調査して、遺産の分け方を決めた上、これをもとに不動産の名義変更や預貯金の解約手続きを進める必要があります。
これらの相続手続きを進めるためには、役所で必要な書類を集めるためにお仕事を休まなければならなかったり、必要な書類の作成方法を調べたり、他の相続人と進め方を話し合ったりする必要があり、その負担が大きい場合も少なくありません。
そのため、何も手続きをせずに、ついつい放置してしまう方もいらっしゃるかと思います。
中には、3年以上、相続手続きをせず、そのままの状態で放置されてしまっているケースもあります。
現在のところは、遺産分割協議に法的な期間制限は無いものの、何もせず放置しておくと、以下のような様々なデメリットが発生するおそれがありますので、注意が必要です。
2 余計な税金を支払うことになるおそれがある
そもそも、相続財産が多い場合には、相続税の申告が必要になる場合があります。
相続税の申告が必要かどうかは、相続財産の内容や相続人の数によって決まり、相続税の申告が必要な場合は、10ヶ月以内に手続きを行う必要があります。
相続税の申告をせず、税金の納付をしないまま放置すれば、税務署から「申告や納税をしなかった」と指摘され、無申告加算税・延滞税・重加算税などのペナルティを課されるおそれがあります。
また、相続税の申告を期限内にしなかった場合には、期限内に申告をしていれば利用できたはずの特例を利用できないなどのデメリットもあります。
そのため、相続税を支払わなければならないケースでは、相続手続きを放置したことで余計な税金を支払うことになるおそれがあります。
3 遺産を勝手に処分されるおそれがある
遺産の分け方を決めずに放置していると、他の相続人や第三者に勝手に遺産を処分されてしまうおそれがあります。
例えば、ご家族が亡くなったことを銀行に知らせなかったために口座が凍結されず、相続財産を管理していた方が無断で預貯金を引き出したり、口座を解約したりしてしまうことが起こり得ます。
また、着物や貴金属など高価な動産が相続財産に含まれている場合には、それらが処分されたとしても、預貯金と違って明確な証拠が残らないことが多いため、勝手に処分した方に対して責任を追及することが難しくなるおそれがあります。
4 相続人の数が増えたり疎遠な相続人が現れたりするおそれがある
過去のご相談の中には、相続手続きを長年放置し続けた結果、相続人が30人以上に増えてしまったケースもあります。
こういったケースについて、相続手続きを専門家に依頼すると、300万円以上の費用が掛かったり、解決までの期間も3年以上もかかったりする場合もあります。
そもそも、相続手続きを長年放置していると、当初の相続人であった方が亡くなり、相続人としての立場が次の世代に引き継がれていくことになります。
例えば、当初は相続人が3人しかいなかったのに、その3人が相続の手続きをしなかった場合、その子や孫、配偶者が他の相続人との間で相続手続きをしなければならなくなります。
相続人の世代が次に引き継がれていくと、その人数が増えてしまうこともありますし、その相続人との間に日頃から交流が無いという可能性も高まります。
相続人の数が増え、その相続人同士に交流がなく疎遠である場合には、より相続手続きを進めることが難しくなります。
例えば、もともとは相続人の全員が同じ地域に住んでいたとしても、その一人が亡くなったために、その地位を引き継いだ方との面識が無かったり、遠方に住んでいてスムーズに手続きを進められなかったりするという可能性が考えられます。
このように、相続手続きを放置すると、相続人の数が増えてしまったり、疎遠な相続人が現れたりすることで、相続手続きを進めることが難しくなってしまうというデメリットがあります。
そのため、相続が発生した際は、先延ばしにせず、まずは専門家に依頼してでも、手続きを進めていった方が良いでしょう。
相続で必要となる戸籍謄本の取得方法
1 相続の手続きをするためには戸籍が必要です

相続の手続きには、不動産の名義変更、預貯金の解約、年金に関するものなど、様々な種類があります。
これらの手続きは、原則として、相続人でなければ行うことができません。
人違いがあってはいけないため、相続の手続きを行うには、相続人であることの証明が必要になります。
相続人であることの証明ができないと、そもそも不動産の名義変更や預貯金の解約等が行えない場合もありますので、注意が必要です。
相続人であることの公的な証明は、戸籍謄本で行います。
2 どの範囲の戸籍が必要なのかは場合によって異なります
⑴ 亡くなった方(被相続人)の戸籍
まず、亡くなった方が生まれてから、亡くなるまでのすべての戸籍謄本が必要です。
戸籍は、結婚をしたり、養子縁組をしたり、転籍したりした場合に、新しく作られるため、そのすべての戸籍謄本が必要です。
⑵ 相続人の戸籍謄本
相続人であることの公的な証明は、戸籍謄本で行います。
相続人が相続手続きを行う場合、手続きを行う相続人自身の戸籍謄本が必要です。
⑶ その他の戸籍謄本
誰が相続人であるかによって、他にも戸籍が必要となることがあります。
例えば、孫が相続人になるようなケースでは、子が死亡していることを証明するために子が生まれてから亡くなるまでの戸籍と、孫の戸籍が必要です。
他方、甥姪が相続人の場合、両親が生まれてから亡くなるまでの戸籍と、兄弟が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍が必要になります。
3 戸籍謄本の取得方法
戸籍は、役所の窓口で取得することになります。
相続人であれば誰でも、亡くなった方の戸籍を取得することができますが、取得の際には、窓口に行かれた方本人の運転免許証といった本人確認書類の呈示を求められます。
亡くなった方の、生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍が必要となるため、結婚や転籍などの理由で、過去に他の都道府県の市区町村に本籍地を移動していたことがあった場合、その分もさかのぼって戸籍を取得する必要が生じます。
そうなると、人によっては数十通の戸籍を取得しなければならないこともあります。
なお、郵送でも戸籍を取得することができます。
郵送で請求する場合と役所の窓口で直接請求する場合とでは、請求にあたって必要となるものが異なりますので、ご注意ください。
4 戸籍謄本と戸籍抄本の違い
戸籍謄本は、同じ戸籍に記載されている方の情報がすべて記載されています。
例えば、夫婦と子が同じ戸籍に記載されている場合に、夫が自分の戸籍謄本を取得すれば、妻と子の氏名や生年月日の情報も記載された戸籍を取得できます。
他方、戸籍抄本は、一部の情報のみが記載された戸籍です。
例えば、先ほどの例で、夫が自分の戸籍抄本を取得した場合は、妻と子の情報は何も記載されていない戸籍を取得することになります。
相続の手続きでは、戸籍抄本ではなく戸籍謄本が必要になることが多いため、注意が必要です。
市区町村役場に行かれた際は、担当者に「戸籍の全部事項証明書をください」などとお伝えいただくと、戸籍謄本を取得することができますので、間違われにくいです。
5 ご不安がある場合はご相談ください
相続手続きを行う際には、実際に金融機関や法務局等に行かれる前に、担当窓口に電話等で必要となる戸籍を確認することをおすすめします。
各機関のホームページなどで、必要書類や手続きの案内をしているところもありますので、参考にしてください。
例えば全国銀行協会では、預金を相続する際に必要な書類を開示しています。
参考リンク:一般社団法人全国銀行協会・預金相続の手続に必要な書類
ただし、各金融機関で異なることもありますので、手続きを行う予定の金融機関へ事前に確認されるのがよいと思います。
法務局では、相続登記の申請をする際に必要な手続きの案内をしておりますので、あわせてご確認ください。
参考リンク:法務局・相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)
とはいえ、「自分の相続でどのような戸籍が必要になるか分からない」「戸籍を適切に集められる自信がない」という方もいらっしゃることと思います。
そのような場合は、私たちにご依頼ください。
弁護士等の専門家が戸籍の取得を代理で行います。
特に、戸籍謄本には、明治や大正時代に作成された古いものが存在し、読み方に専門的な知識を必要とします。
また、相続人が複数いる場合は、戸籍謄本だけでも数十通必要になる場合もあります。
そのため、古い戸籍を取得する必要がある場合や相続人が複数いる場合は、どの戸籍が必要か判断をしたり数多くの戸籍を読み解いたりする必要がありますし、代理で行った方が、確実かつスムーズに戸籍の取得を進められる可能性がありますので、お気軽に私たちまでご連絡いただければと思います。
ご家族が亡くなられた際にすぐ必要となる手続
1 身内が亡くなったときにすぐにやるべきこと

人が亡くなると、葬式の準備や役所への届出など、様々な手続きが必要となりますが、身内が亡くなるということは人生で何度も経験することではありませんので、不慣れな方も多いのではないでしょうか。
以下では、身内が亡くなって遺産を相続した後にすぐにやるべきことを解説していきます。
2 死亡診断書の取得と死亡届の提出
⑴ 死亡診断書の取得
身内が亡くなったときには、まずは死亡診断書を取得する必要があります。
死亡診断書は、その方がどのように死亡したかなどが記載されている書類です。
亡くなった方が生前治療をしていた病気が原因で死亡した場合には、主治医に死亡診断書の作成を依頼して、取得します。
上記以外で亡くなった場合や死因が不明な場合には、死亡診断書の代わりに医師による死体検案書を作成してもらう必要があります。
なお、死亡診断書も死体検案書も発行には費用がかかります。
⑵ 死亡届の提出
死亡診断書を取得した後は、市町村に死亡届を提出します。
死亡届と死亡診断書は合わせて1枚の用紙となりますので、用紙の左側の死亡届の欄に亡くなった方の氏名や住所などを記載して作成します。
※参考リンク:死亡届/法務省
死亡届の提出先は、亡くなった方の本籍地のある市町村、亡くなった場所の市町村、あるいは届け出る方の所在地の市町村のいずれかです。
名古屋市内の病院で亡くなったのであれば、市内の区役所に提出することになります。
死亡届は亡くなったことを知ってから7日以内に提出する必要がありますし、これを提出しなければその後の相続の手続きを進められませんので、ご注意ください。
⑶ コピーを取っておく
提出する死亡届と死亡診断書は、提出前にコピーを取っておくとよいです。
葬儀や生命保険金の受取りなど、その後の相続の手続きに必要になるためです。
ここでコピーを取り忘れた場合は、死亡届の記載事項証明書を請求しなければならなくなる可能性もありますので、注意が必要です。
3 火葬許可証の取得
死亡届を提出するのとあわせて、葬許可申請書を提出します。
申請用紙は市町村の窓口にありますので、これに必要事項を記入して提出すると、市町村から火葬許可証が発行されます。
火葬許可証を取得できれば、葬儀や火葬を行うことができるようになります。
取得した火葬許可証は、遺体を火葬する火葬場に提出する必要がありますので、大事に保管しておいてください。
4 葬儀会社が代行してくれることもあります
上記の手続きは、葬儀会社がその一部を代行してくれることもあります。
葬儀では、やらなければならないことや決めなければならないことも多いため、手続きをする余裕がない場合には、上記の手続きを代行してもらうのもよいかと思います。
様々な情報を掲載しています
相続に関する基本的な情報から、ある場面に特化した情報まで様々な情報を掲載しています。相続についての情報を集めているという方は、一度ご覧ください。