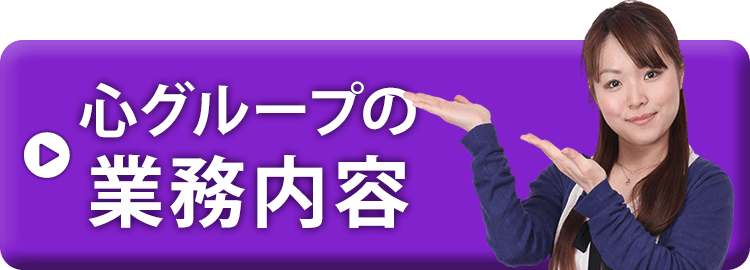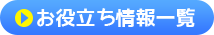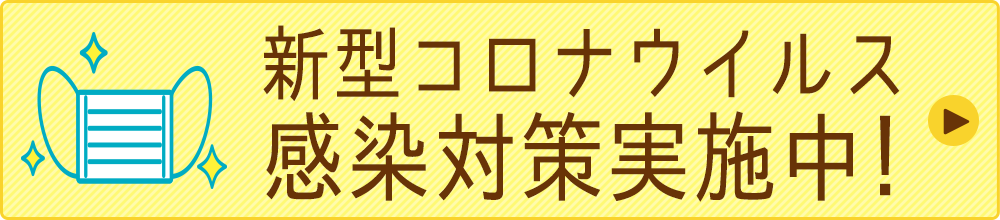所在地について
名古屋駅から近いところにオフィスがありますので、ご相談にお越しになる際もとても便利です。予約をとっていただけば、お仕事の帰りやお休みの日にもご相談いただけます。
相続案件では、なぜ、弁護士・税理士の両方に相談すべきなのですか。
1 相続案件の適切な解決には法律・税金両方の理解が必要

相続税は、誰が、どの財産を相続するかによって、適用できる相続税の軽減措置等が異なり、税額が大きく変わります。
例えば、配偶者の税額軽減特例を利用しますと、配偶者の取得した相続財産が1億6000万円又は法定相続分相当額のいずれか多い金額までは、相続税がかからなくなります。
このような相続税の軽減制度を知らないまま、遺言書を作成したり、遺産分割協議書を作成したりしますと、思ってもいなかった相続税を支払わなければならなくなることもあります。
したがって、相続案件を法律・税金の両方の観点から適切に解決するためには、両方の理解が必要です。
2 同一グループ内に弁護士・税理士がいる強み
通常、弁護士・税理士に相談する場合、別々の事務所に相談することになります。
ただ、そうするともう一度最初から相談内容を説明しなければならない手間がかかりますし、相談料も二度かかってしまうことになります。
同一事務所や同一グループ内に弁護士・税理士が所属しているところであれば、このような二度手間や相談料の二重払いを避けることができます。
3 弁護士と税理士で連携できる環境を整えています
私たちは、お客様へ負担をかけることがないように、弁護士法人心と税理士法人心とが連携できる環境を整えています。
特に、名古屋市では、弁護士法人心の弁護士と税理士法人心の税理士が、同一建物内で勤務しており、コミュニケーションも密に取り、共同の勉強会も頻繁に行うなど、法律・税金の両方の観点から相続案件を適切に解決できるよう万全の体制を整えております。
相続に関する相談料は原則無料となっていますので、名古屋市やその近郊にお住まいの方で、遺産相続にお悩みの方は、まずはフリーダイヤルやメールフォームからお気軽にお問合せください。
心グループのご案内
1 各企業が連携

より幅広くお悩みへの対応ができるように、弁護士法人心、税理士法人心、社会保険労務士法人心、株式会社心相続、株式会社心保険、株式会社心経営、株式会社心デザインなどの複数の企業が連携できる体制をとっています。
相続では、弁護士法人心に所属する弁護士、税理士法人心に所属する税理士や株式会社心相続に所属する社員がお客様の相続案件へ対応いたします。
2 相続を集中的に取り扱う専門家がお客様の相続案件を担当
弁護士法人心と税理士法人心には、それぞれ相続を集中的に担当する弁護士や税理士がいます。
これは、集中的に相続業務を取り扱うことで、一般的な弁護士・税理士よりも圧倒的に相続案件の経験を積むことができ、専門的なノウハウを身につけることができるからです。
また、相続案件を適切に解決するためには、法律・税金の両方の知識や理解が欠かせません。
私たちは、相続を集中的に取り扱う弁護士・税理士が必要時に連携して案件解決に尽力できるようにしていますので、安心です。
3 各事務所の所在地
各事務所は、いずれも最寄り駅から徒歩圏内の場所に設置しております。
例えば、弁護士法人心の本部や弁護士法人心 名古屋法律事務所は、名古屋駅の太閤通南口から徒歩2分のところにあります。
4 相続のご相談は私たちにお任せください
遺言・遺産分割・相続税申告等の相続手続きでお困りの方は、まずはフリーダイヤルやメールフォームからご連絡ください。
各種の専門家やスタッフがより良い解決へ向けて対応させていただきます。